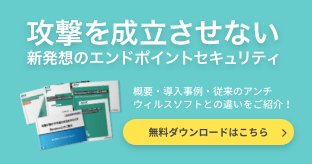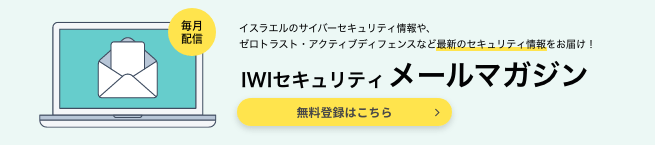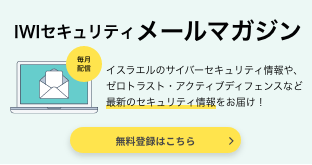情報セキュリティインシデントとは、情報の安全を脅かす事故や問題のことです。
被害は企業内部にとどまらず、顧客や取引先にも影響する恐れがあります。
本記事では、インシデントの具体例や原因、防止策について解説します。
情報セキュリティインシデントへの対策を検討されている方には、「不正の先手を打つ情報漏えい対策製品CWAT(シーワット)」 の概要資料をご提供します。
CWATには、以下の特徴があります。
情報漏えい防止機能の特長
- 情報漏えいのもととなる印刷、外部記憶媒体、メール、Webの利用を柔軟に制御可能
- キーワードチェックにより自動で重要情報を検出し保護(機密キーワードは個別に変更可能)
- 部署やユーザーの権限に合わせてポリシー(ルール)を設定し、部署/ユーザー単位の監視・制御が可能
- 独自の暗号化機能によるファイル保護と閲覧制限(万が一漏えいしても閲覧不可)
- 重要情報に対する不正操作(コピー、ファイル名変更)の即時検知と管理者通知
- 詳細な操作ログ取得によるリアルタイムの監視と不正操作の自動制御機能
- 日/英/韓/中(繁体・簡体)マルチ言語対応によるグローバルなセキュリティ対策
退職者による情報漏えい対策を検討されている方におすすめの資料
-
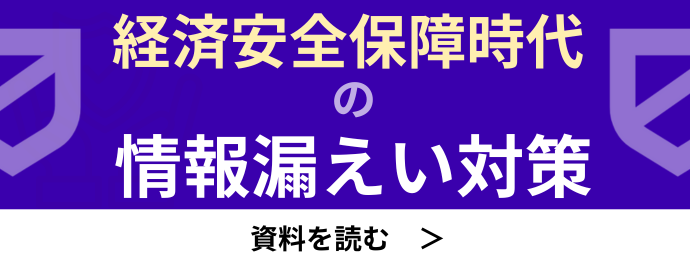
経済安全保障時代の
情報漏えい対策最新の法規制動向や内部不正の実例を踏まえ、DLPによって企業の情報漏えい対策を強化する方法について紹介した資料
-
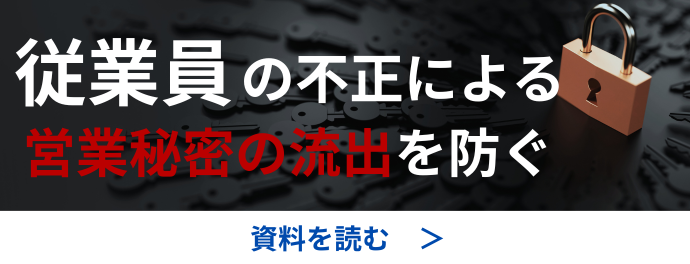
従業員の不正による
営業秘密の流出を防ぐ従業員による内部不正事案の現状や発生原因を紐解きながら、
被害を未然に防ぐ方法をご紹介 -

技術流出対策
ユースケース10選現場で実践されている、DLPを用いた情報流出対策のユースケースをご紹介
目次
情報セキュリティインシデントとは
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)はセキュリティインシデントについて、以下のように定義しています。(「中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き」より引用)
セキュリティインシデントとは、セキュリティの事故・出来事のことです。単に「インシデント」とも呼ばれます。例えば、情報の漏えいや改ざん、破壊・消失、情報システムの機能停止またはこれらにつながる可能性のある事象等がインシデントに該当します*1。
また、情報の社外への流出や書き換えなどに直接関わる事象だけでなく、それらにつながる可能性のある事象もセキュリティインシデントに該当します。
情報セキュリティインシデントがもたらす恐れのある影響
情報セキュリティインシデントがもたらす恐れのある影響として、以下が挙げられます。
- レピュテーションリスク(企業に関するネガティブな評判が拡散され、信用やブランドが失墜するリスク)が高まる可能性がある
- インシデントの原因調査や再発防止策の実施に多大な負荷がかかる可能性がある
- 経済的な損失につながるリスクがある
レピュテーションリスクが高まる可能性がある
情報セキュリティインシデントが発生すると、企業に対する社会からの評価が低下する場合があります。特に、情報漏えいなどの被害は、多くの場合、取引先や顧客にとって大きなリスクと受け止められます。
その結果、企業は信頼性を失い、取引先から取引を停止される、あるいは顧客が商品やサービスを選ばなくなるといった事態に発展するケースも少なくありません。
これらの影響は企業の経営に深刻なダメージを与えるため、インシデントの未然防止が極めて重要です。
インシデントの原因調査や対策に多大な負荷がかかる可能性がある
情報セキュリティインシデントが発生すると、その原因調査や対策に多大な負荷がかかる可能性があります。
一度インシデントが起きると、企業は被害の拡大防止や再発防止のために、原因の究明や被害者への補償などを行う必要があります。
これらの対応には、かなりの人的コストや金銭的コストがかかります。深刻度によってはすべての事業活動を停止して対応を行う必要もあります。
さらに、新たなセキュリティ製品の導入や、社内システムの復旧が必要となる場合もあり、これらの対策にはさらなる負担を伴う可能性があります。
このように、情報セキュリティインシデントへの対応は企業の通常業務を圧迫し、経営に大きな影響を与える可能性があるため、事前の予防策を講じることが極めて重要です。
経済的な損失につながるリスクがある
内部不正による情報漏えいや横領などが行われた場合、企業に直接的な経済的損失を引き起こすだけでなく、顧客や取引先への補償、損害賠償なども発生することがあります。
また、サイバー攻撃では、システムの復旧費用やランサムウェアによる金銭的被害が高額になるケースも多く、数千万円から数億円にのぼることもあります。
復旧やインシデント対応後も、影響を受けた顧客への対応などを行っていく必要があります。
情報セキュリティインシデントによって情報漏えいが生じた事例
以下の例は、情報セキュリティインシデントによって情報漏えいが生じた事例です。
・医薬品メーカーが利用するサービスの脆弱性を狙った攻撃により、個人情報が漏えいした事例*2
・大手IT企業のソフトウェアを狙ったランサムウェア攻撃で、約77億円の身代金を要求された事例*3
情報セキュリティインシデントの詳細や事例について知りたい方は、関連記事をご参照ください。
情報漏えいの事例13選!有名な被害事例を一覧表でわかりやすく紹介
情報セキュリティインシデントが発生する具体的な要因
情報セキュリティインシデントが発生する具体的な要因として、以下が考えられます。
- 内部要因
- 外部要因
内部要因
組織内部の関係者による情報の不正な持ち出し
セキュリティインシデントの内部要因の具体例として、組織内部の関係者によるデータの不当な複製や持ち出しが挙げられます。
例えば、社内で保管すべき重要情報を無断でUSBなどの外部記憶媒体にコピーすることや、共有フォルダに複製するなどの行為が該当します。
また、情報の取扱いに関する知識不足により、意図せずに情報を外部に持ち出してしまうケースも少なくありません。
そのため、情報の保管方法の見直しや、情報の外部への持ち出しを制限するセキュリティ製品を導入するといった対策が必要です。
誤送付や紛失などのヒューマンエラー
情報の誤送付や紛失などのヒューマンエラーについても、セキュリティインシデントの内部要因に当たります。
主に組織内部関係者の不注意によって、意図せず情報が流出してしまうケースがあります。以下は、ヒューマンエラーの例です。
- メールやFAXなどの送信先を間違えてしまう
- 外部記憶媒体や電子端末を紛失してしまう
- 社外秘の情報を誤って公開してしまう
ヒューマンエラーを防止するためには、社内の情報管理に関するルールを再確認するとともに、セキュリティ製品を活用して誤送信防止やアクセス制限といった実効性のある対策を講じることが求められます。を講じることが求められます。
権限を濫用した情報への不正アクセス
権限を濫用した情報への不正アクセスも内部要因の情報セキュリティインシデントに該当します。
例として、業務用のアクセス権限の濫用や、許可されていない端末からの重要情報への不正アクセスが含まれます。
これらの行為は、個人情報の不正閲覧や機密情報の盗難など、深刻な問題を引き起こす可能性があります。
こうした不正アクセスを防ぐためには、従業員のアクセス権限を必要最小限の範囲に制限したり、秘密保持契約を締結したりすることが有効です。
また、権限を利用した操作のログを継続的に監視することができる内部不正対策ソリューションの導入も効果的です。
外部要因
DoS攻撃
DoS攻撃(Denial of Service Attack)とは、主に標的の組織のサービスを妨害することを目的に、ウェブを介して行われる攻撃のことを指します。
DoS攻撃によりシステムが正常に動作できなくなることで、さらなる攻撃の被害を受けるリスクが高まります。
攻撃の具体的な手段としては、標的となるサーバーやネットワークに対して短時間で大量のトラフィックやデータを送信することで、システムダウンや応答速度の低下を引き起こします。
また、複数の機器から大量のデータを送信する攻撃をDDoS攻撃(Distributed Denial of Service Attack)といいます。DDoS攻撃は、攻撃者が多数のコンピューターを踏み台にして行われます。
マルウェアへの感染
マルウェアとは、トロイの木馬やランサムウェアなど、コンピューターシステムに対して攻撃を行う、悪意のあるソフトウェアを指します。
マルウェアに感染すると、重要情報の窃取やデータの暗号化による端末の使用不能など、深刻な被害が生じる可能性が高まります。主な感染経路として、マルウェアが埋め込まれたファイルの開封や、不正なウェブサイトへのアクセスなどが挙げられます。
近年では、感染したデータの復元と引換えに金銭を要求するランサムウェアや、感染したパソコンから他のデバイスへ感染を拡大させる攻撃も増加しています。
ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃とは、システム内の脆弱性が修正される前に、その脆弱性を狙って実行される攻撃を指します。システム内の脆弱性とは、セキュリティ上の弱点を指し、攻撃者はこれを介して標的への攻撃を行うことが多いです。
開発元が脆弱性を見落としたり、修正対応が長引いたりすることで、ユーザーがゼロデイ攻撃の被害に遭う可能性が高まります。
アプリケーションの脆弱性を悪用する攻撃
アプリケーションの脆弱性を悪用する攻撃の代表例として、SQLインジェクション攻撃やクロスサイトスクリプティングなどが挙げられます。
SQLインジェクション攻撃とは、データベースを制御する際に広く使われている言語(SQL)を標的のサイトへ不正に入力(インジェクション)する攻撃のことを指します。
その結果、標的となるサイトのデータベースへ不正アクセスを行い、重要情報を窃取したり、システム自体を改ざんしたりするケースが見られます。
Webアプリケーションの脆弱性を悪用して、スクリプトを埋め込む攻撃であるクロスサイトスクリプティングも、アプリケーションの脆弱性に基づく攻撃の主な例として挙げられます。
標的型攻撃
標的型攻撃とは、特定の企業や団体が所有する情報資産を狙ったサイバー攻撃のことを指します。
標的型攻撃のよくある手法として、標的とする組織のステークホルダーを装い、マルウェアを埋め込んだ偽の業務連絡を送信することで、侵入を狙うケースが多く見られます。
また、マルウェアを仕込んだ偽のサイトへ誘導するメールを送ることや、標的となる組織が日常的に利用するサイトを改ざんして悪意のあるプログラムを仕込む「水飲み場攻撃(標的がよく訪れる正規サイトを改ざんして感染させる手法)」も確認されています。
偽のメールやサイトは、本物と見分けがつきにくい巧妙な作りとなっているため、特に注意が必要です。
災害などその他原因によるシステムの不具合
災害などその他の原因によるシステムの不具合も、情報セキュリティインシデントに当たります。具体的には、以下のような要因によってシステムの障害が生じる可能性があります。
- 洪水や火災などの災害による物理的な故障
- 連携している外部の製品の障害
- 自社のサーバーや電子機器自体の故障や不調
これらを要因とするシステムの障害によって、情報資産の消失や業務の停止などの損害が生じる可能性があります。
内部関係者による情報漏えいリスクの重要性と社会的注目
情報漏えいは、外部からのサイバー攻撃だけでなく、企業内部の人間、特に退職者や元従業員による意図的な不正行為によっても発生します。実際に、過去には内部関係者による営業秘密の持ち出しや、顧客情報の流出といった深刻な事例が発生しており、企業の信頼や業績に大きな影響を与えました。
近年では、経済安全保障の観点からもこうした内部不正に対する注目が高まっており、政府も対応を強化しています。2025年には経済産業省が「技術流出対策ガイダンス」を発表し、退職時の情報管理や秘密保持契約の徹底など、企業が講じるべき具体的な対策を明示しました。
これらの背景を踏まえると、内部関係者による情報漏えいリスクへの理解を深め、再発防止に向けた実効性ある対策を講じることは、企業が信頼性を維持し、競争力を確保するために極めて重要です。
情報セキュリティインシデントの対策
情報セキュリティインシデントを生じさせないための対策として、以下が挙げられます。
- セキュリティを重視した組織体制の整備
- 従業員の情報リテラシーを向上させる
- 内部不正対策製品を有効活用する
- 未知の攻撃にも対応可能なソフトウェアを用いる
- 社内の重要情報や権限の管理状況を確認する
セキュリティを重視した組織体制の整備
情報セキュリティインシデントを防止するために、セキュリティを重視した組織体制の整備が重要です。具体的には以下のような取組みが効果的です。
- 情報セキュリティの分野に関して豊富な知識を有する担当者や専門部署の設置
- 情報セキュリティインシデントの潜在的要因となる社内状況の明確化
- 端末や権限などの社内の情報管理に関するルールの定期的な見直しと更新
さらに、万が一情報セキュリティインシデントが発生した場合に備えて、インシデント対応の手順や関係者の役割を事前に明確化し、定期的に確認しておくことも重要です。
従業員の情報リテラシーを向上させる
情報セキュリティインシデントは、従業員の情報リテラシー不足による過失や不適切な行動が要因となって発生するケースが少なくありません。
そのため、情報を適切に取り扱うための基本的な知識や、インシデントの要因となり得る状況に遭遇した際の適切な対処方法などを実践的に教育することが、インシデント防止において重要です。
また、定期的な研修やテスト、ガイドラインの周知など、社内の情報管理に関するルールを徹底させるための取組みも、インシデントの抑止に効果的です。
未知の攻撃にも対応可能なソフトウェアを用いる
シグネチャ型のAV(アンチウィルス)など、従来のソフトウェアでは、既知の脆弱性に対する対策は施されているものの、未知の攻撃手法に対しては十分な対応ができない場合があります。
そのため、AIや機械学習を活用して未知の脅威を検知・防御できる次世代型のセキュリティソフトウェアを導入することが効果的です。
また、ソフトウェアが常に最新の状態であることも重要です。アップデートを怠ると、修正されていない脆弱性が残り、その脆弱性を悪用した攻撃を受けるリスクが高まります。
社内の重要情報や権限の管理状況を確認する
社内の重要情報や権限の管理状況を定期的に確認することで、情報管理体制の現状を整理し明確にすることができます。これは情報セキュリティインシデントを抑止するうえで重要です。
それらが適切に把握できていない場合、意図せず情報が外部に流出したり、知らないうちに権限が第三者へ譲渡されたりするリスクが高まります。
具体的な対策として、各情報に対して権限が付与されている人員をリスト化し、権限の所在を可視化することが挙げられます。
ただし、管理すべき情報が膨大になることもあるため、重要情報のアクセス権限を管理可能なシステムなどを活用して一元的に管理することも有効です。このようなシステムを導入することで、効率的かつ正確な情報管理が可能になります。
- CWATの資料を請求する
役職や業務実態に即した情報管理ルールを柔軟に設定可能
内部不正対策製品を有効活用する
内部不正対策製品は、従業員の不適切な行動や意図的な情報漏えいを検知し、防止するために設計されています。これらの製品は、以下のような機能によって、内部不正のリスクを軽減します。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| アクセス制御 | 重要な情報へのアクセスを適切に制限し、不必要なアクセスを防ぎます。 |
| データ暗号化 | 機密情報を暗号化し、漏えいのリスクを低減します。 |
| ログ監視 | 端末やアプリケーションの操作ログを収集し、不正行為を記録します。 |
| デバイス制御 | USBメモリなどの外部記憶媒体の使用を制限し、データの不正な持ち出しを防止します。 |
| データの重要度を識別 | ファイルに含まれるキーワードなどから自動的に重要な情報を識別し、対象のファイルを保護します。 |
| ファイル保護 | 独自の暗号化機能によりファイルを保護し、不正な閲覧を制限します。 |
| リアルタイム検知 | 重要情報に対する不正操作(コピー、ファイル名変更など)を即時に検知し、管理者に通知します。 |
- CWATの資料を請求する
情報漏えい対策をご検討の方
これらの製品を導入する際は、組織の特性やニーズに合わせて適切な設定を行い、定期的に運用状況を確認することが重要です。また、製品の導入だけでなく、従業員への教育や啓発活動と組み合わせることで、より効果的な内部不正対策が可能となります。
情報セキュリティインシデントについてよくある質問
情報セキュリティインシデントが生じた時にとるべき対応はどのようなものですか?
情報セキュリティインシデントが発生した場合、以下の対応を行うことを推奨します。
- 早急に責任者や担当者へ連絡する
- さらなる被害拡大を抑えるための緊急措置を講じる
- インシデントの原因や被害状況を明らかにするための調査を実施する
- 関係者や一般に対して状況を適切に公表・通知する
- 二次被害を防ぎ、状況を改善するための対策を講じる
- インシデントの再発を防ぐための施策を実施する
情報セキュリティインシデントの発生を完全に防ぐことは極めて困難です。そのため、インシデント発生後の対応手順を事前に把握し、準備しておくことが非常に重要です。
適切な事前準備と迅速な対応により、被害の最小化と早期復旧が可能となります。
情報セキュリティインシデントの内部要因と外部要因には、どのような違いがありますか?
内部要因は、主に従業員など組織内部の関係者の行動によって発生するインシデントです。メールの誤送信やUSBメモリによる情報の不正持ち出し、権限の濫用による不正アクセスなどが挙げられます。
一方、外部要因は、サイバー攻撃(マルウェア感染、DoS/DDoS攻撃、標的型攻撃など)や、アプリケーションの脆弱性を突いた攻撃、さらには自然災害によるシステム障害など、組織外部からの影響によって発生するものです。
情報セキュリティインシデントの発生を早期に検知するには、どのような方法がありますか?
早期に検知するためには、以下のような取組みが有効です。
- ログ監視や不正操作を検知可能なソリューションの導入
- サーバーやネットワーク機器の異常を検知するためのIDS/IPS(侵入検知・防御システム)の活用
- ファイルやデータベースへのアクセス状況を可視化し、通常と異なる挙動をリアルタイムで把握する
- 社内外の脆弱性情報を定期的に収集し、早期に対策を講じる体制の整備
インシデントによる情報漏えいを防ぐ「CWAT」
CWATは、表面的な対策ではなく“根本原因の抑止”にこだわった情報漏えい対策ツールです。
キーワード識別・経路監視・不正操作の即時検知まで、企業の現場に即したセキュリティを柔軟に設定可能です。
CWATの特徴
- 部署ごとに機密情報にあたるキーワードを設定することで、キーワードが含まれるファイルを自動で識別し保護
- Web、メール、USBメモリ、スマートフォン、印刷など、エンドポイントを起点とする情報の漏えい経路を網羅的に監視&制御
- 部署やユーザーの利用実態に合わせてポリシー(ルール)を設定し、部署/ユーザー単位の監視・制御が可能
- 独自の暗号化機能によるファイル保護と閲覧制限(万が一漏えいしても閲覧を不可にする)
- 重要情報に対する不正操作(コピー、ファイル名変更)の即時検知と管理者通知
- 詳細な操作ログ取得によるリアルタイムの監視と不正操作の自動制御機能
- 日/英/韓/中(繁体・簡体)マルチ言語対応によるグローバルなセキュリティ対策
退職者による情報漏えい対策を検討されている方におすすめの資料
-
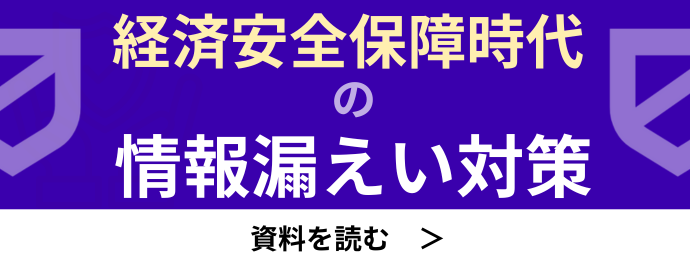
経済安全保障時代の
情報漏えい対策最新の法規制動向や内部不正の実例を踏まえ、DLPによって企業の情報漏えい対策を強化する方法について紹介した資料
-
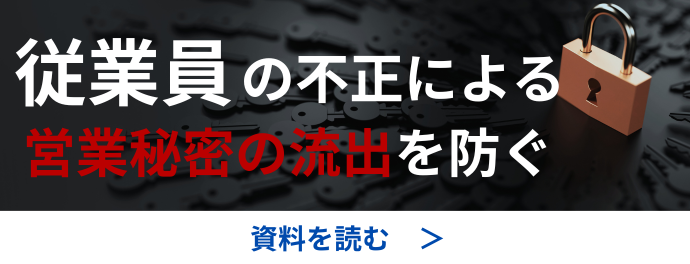
従業員の不正による
営業秘密の流出を防ぐ従業員による内部不正事案の現状や発生原因を紐解きながら、
被害を未然に防ぐ方法をご紹介 -

技術流出対策
ユースケース10選現場で実践されている、DLPを用いた情報流出対策のユースケースをご紹介
出典 (参考文献一覧)
※1 IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 | 中小企業のための セキュリティインシデント 対応の手引き (参照日:2025-05-07)
※2 JD Supra | Bristol Myers Squibb Informs Employees of Leaked SSNs Following MOVEit Data Breach (参照日:2025-05-07)
※3 CNN.co.jp|米ソフトウェア企業にランサムウェア攻撃、77億円の身代金要求 (参照日:2025-05-07)
監修者プロフィール

靜間 隆二(セキュリティイノベーション本部 CWAT製品企画部 部長)
当社入社から20年以上、情報セキュリティの事業に携わる。サイバー攻撃からの対策、内部不正による情報漏えい対策の両側面で専門知識を有する。中小~国内を代表する上場企業まで幅広いセキュリティ対策を支援した実績あり。

株式会社RE-HEART 代表取締役CEO
小山雄太
Webシステム開発とITコンサルティングを中心に、要件定義から設計・開発、および運用支援まで多様な経験を持つ。近年はAWSを基盤としたクラウドインフラの設計・構築に注力し、
クライアント企業様に向けたセキュリティ対策やDevOps推進を支援する。